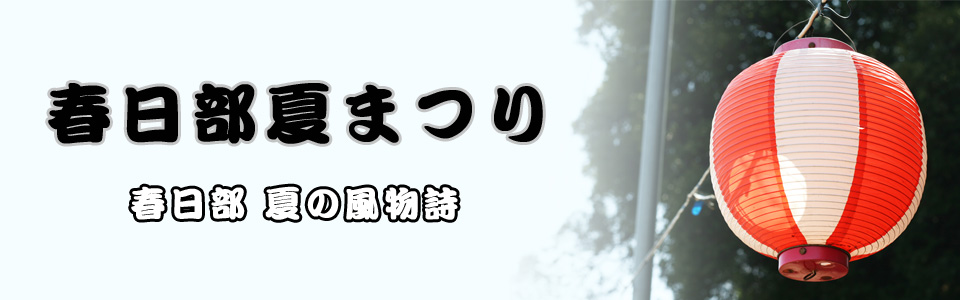底抜け屋台

底抜け屋台の歴史
江戸時代は宝暦(1751~1764)から明治にかけて、江戸から各地で見られた屋台です。構造は、四本柱に日除けの天幕を張り、床はなく、囃し手は中で歩きながら演奏します。埼玉県では文政9年(1826年)の川越祭りを描いた埼玉県指定文化財「川越氷川祭礼絵巻」の中に底抜け屋台が描かれている姿を確認できます。
「川越氷川祭礼絵巻」に描かれている底抜け屋台は4人で担いでいるのが確認できます。かつての底抜け屋台は4人が肩から晒したたすきにそれぞれ屋台の柱を引っ掛けて、屋台を持ち上げ、練り歩いていたようです。現在、春日部夏まつりで使用している底抜け屋台には車輪が付き、他の地域で用いられている底抜け屋台も車輪付きがほとんどのようです。
屋台と山車の違い
山車とは人形山車や鉾のように高くつきでている曳山(祭礼の山車)のことを指します。 屋台とは突き出ているものがなく屋根があり、様々な芸能を披露できるように舞台を兼ね備えているものが屋台です。
屋台によって手前に踊り舞台、奥に囃子のスペースを持ったもの、もっと豪華になると屋台本体の左右に張出し舞台を架設してさらに大きくしたものもあります。
しかし、江戸時代この屋台も八代将軍吉宗による亨保の改革により華美な屋台禁止令が出され、姿を消したものもあるようです。しかし、やっぱりお祭り好きな江戸っ子達。比較的小さな踊り屋台と囃子用の底抜け屋台をペアーにした型にしたというエピソードもあります。
屋台と神輿の運行順は、神輿の通る道を神楽が囃子で清めるため屋台は神輿の前を運行します。鉾やダンジリは神輿の警固の役割のため神輿の後ろになります。
仲町の屋台
明治初期に造られたもので総けやき造りで、正面の鬼板には鶴の彫刻、懸魚には亀の彫刻、袖には唐獅子の彫刻が施されており、 天井には牡丹の画が描かれています。
大きすぎることと100年以上も経っているため昭和63年に改修し、縮小されました。 山車と屋台の違いを読んでいただければ仲町の屋台は山車ではないことがご理解いただけると思いますが、屋台手前は踊り、舞台奥が囃子のスペースになっています。
昔はこの舞台スペースで町内の旦那衆に呼ばれた不動院野の神楽師などが飲食の接待や浴衣のおみやげなどをもらい 神楽やお囃子をご披露していました。現在では私達底ぬけ屋台のメンバーが江戸囃子のおけいこの成果を、未熟ですが皆さんにご披露させていただいております。